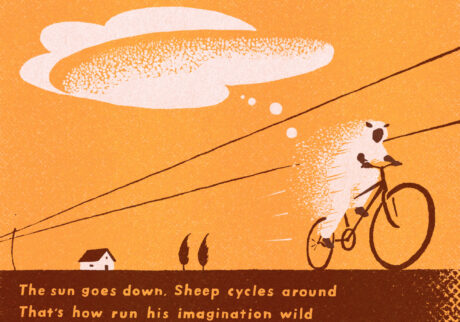INTERIOR 部屋を整えて、心地よく住まうために。
アンティークとグリーンに囲まれた、セーヌ川沿いの公営住宅へ。イラストレーターのシビル・シュヴリエさんの住まい方。April 14, 2024
パリやその周辺に暮らす34組の住まいを訪ねて、部屋づくりの秘訣と、そこに詰まったベターライフのヒントを追いかけた&Premium特別編集MOOK(2024年2月発売号)「&Paris パリに暮らす人の、部屋づくり」。その中からここでは、イラストレーターのシビル・シュヴリエさんの住まいを特別に公開します。

セーヌ川沿いの家をアトリエとしても使う。
パリ13区の、セーヌ川に面する近代建築に住むイラストレーターのシビル。家族はパートナー、2人の息子、そして犬と猫が1匹ずつ。2005年に入居したというアパルトマンはデュプレックス(2フロアある
物件)。広さは80㎡で、1階にはリビング兼ダイニングルームとキッチン。2階に息子の部屋が2部屋。その上のメザニン(中2階)はシビルとパートナーの寝室で、リビングとメザニンの2か所に広々としたバルコニーがある、贅沢な物件だ。
「ここはパリ市が所有する公営住宅。以前は13区のビュット・オー・カイユという、古い住宅が集まる地区に住んでいました。今よりずっと小さいアパルトマンで、次男が生まれたとき、パリ市に入居希望を提出しました。その6か月後にこの物件に当たったんです」。家賃が安い公営住宅は競争が激しく、公務員や収入の少ない家庭が優先される。半年で理想の物件に当選したのは、非常にラッキーだったという。
彼女のアトリエはリビングの一角にある。「朝、犬の散歩に行き、そのあと制作に取りかかります。9〜12月は、発注が殺到する時期。受注から発送までひとりで行うので、創作の時間が少ないのが悩みですね」
自分がイラストレーターになるとは想像もしなかった、とシビル。子どもの頃からクラシックバレエに打ち込み、将来の夢はダンサーだった。パリの大学で映画と文学、演劇を学び、学生時代に書いたシナリオは賞もとった。そのシナリオで短編映画を撮影したこともあった。「映画の製作チームは大所帯。もともとひとりで書くのが好きだったので、大勢で働くことに難しさを感じ、映画の道を断念することにしたんです」
大学卒業後は出版社に勤務。その後、グラフィックデザイナーのフィフィ・マンディラックの下で働きながら、’01年に始めたブログが次第に評判になっていった。

ブログの絵がきっかけで イラストレーターに。
「もともと文章を書くのが好きでした。感じたことやメッセージをブログに書き、その世界観に合うイラストも自己流で描くように。イラストのスタイルが確立してくると、絵の仕事の依頼がどんどん増えて、驚きました。自分のイラストを用いてカードやノートを作りたい、と考えるようになり、パペトリー(紙製品を扱うショップ)も設立。まさか自分が絵を描いたり、カードを作ったりするとは思いもしなかったので、人生はわからないものですね」
家具や食器はブロカント(フリーマーケットやセカンドハンド)、エマウスで購入。エマウスとは、1949年にピエール神父が設立したリサイクル事業。不用品を回収し、安価で販売し、その収益でホームレスなどの社会復帰を助ける、非営利団体が運営している。「特に、郊外のイヴリー・シュル・セーヌのエマウスは安くて質のいい家具が多くて。一時は頻繁に通っていました」
パートナーは会社員。シビルが24歳のときに出会ったが、特に法律婚をする必要性を感じず、彼女の希望でパックス(連帯市民協約)を選択した。息子は2人とも18歳以上だし、家族それぞれのスペースも必要。
「私とパートナーの寝室があるメザニンは、入居時にはなかったんです。この物件は寝室が2部屋だけ。だけど、息子たちの部屋も必要で……。いろいろ考えた末、友人の建築家に頼んで中2階を作りました。おそらく転居する際に壊さなくてはいけませんが、デッドスペースに部屋を作ったのは、とてもいい考えでした。ただ、天井高が1・2mなので、頭をぶつけないように注意が必要!」
おいしいものが大好きで、料理も得意。とはいえ、とにかく仕事が忙しいため、「フーデット」を利用することも。オーガニックの野菜など、良質な食材がレシピとともに配達され、30分以内に料理が出来上がるという便利なサービスだ。
「ひとりで制作から発送までを賄うのは大変。今のアトリエも手狭なので、そろそろアトリエ兼ショップをパリ市内に構え、アシスタントを雇う予定です。それが完成したら、個展を開催したいなと。日本の紙や文具は良質で、見るたびに感心します。バカンスは日本で過ごして、文具店巡りをしてみようと思います」
Sibylle Chevrier シビル・シュヴリエ
仏・ポワチエ出身のイラストレーター。紙製品を扱うブランド〈パピヨナージュ〉代表も務める。パリの公営住宅に家族と暮らす。室内とバルコニーには花と緑がいっぱい。
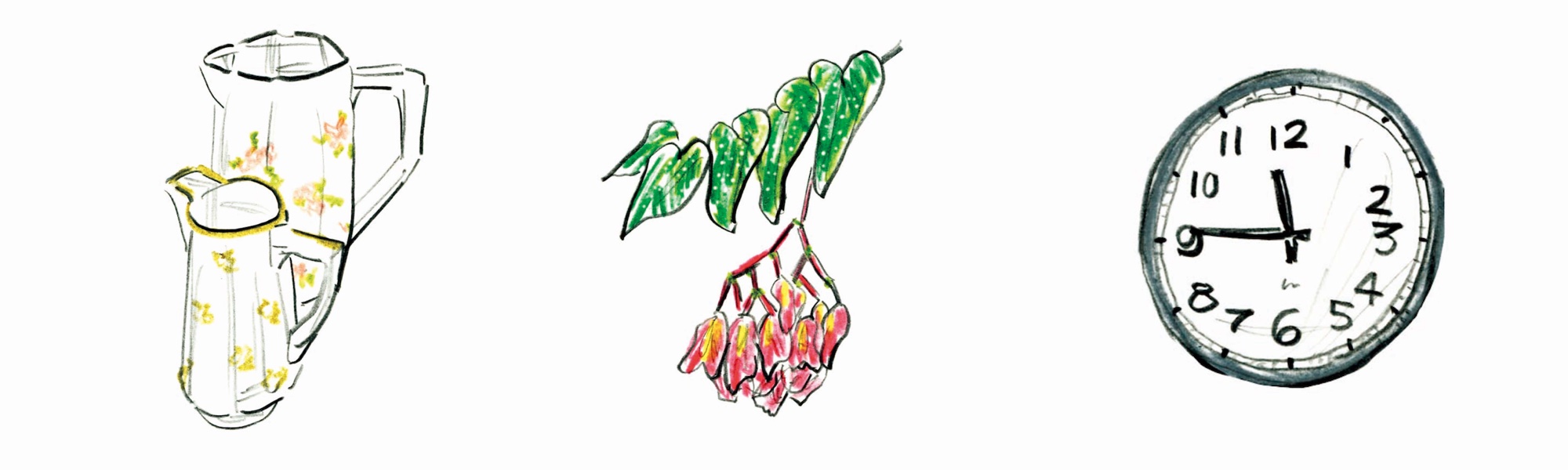
photo : Sumiyo Ida text : Miyuki Kido