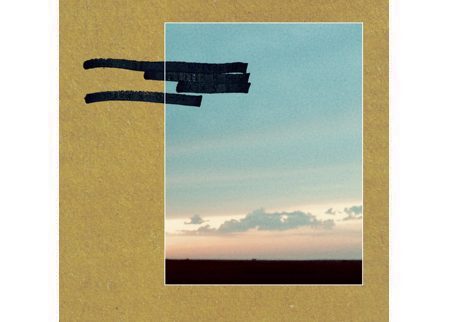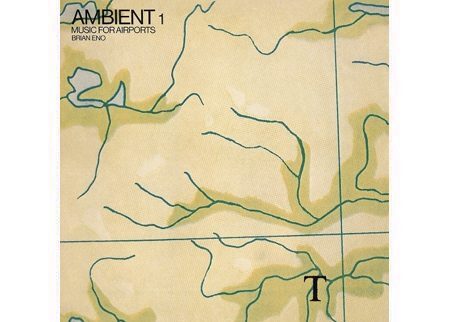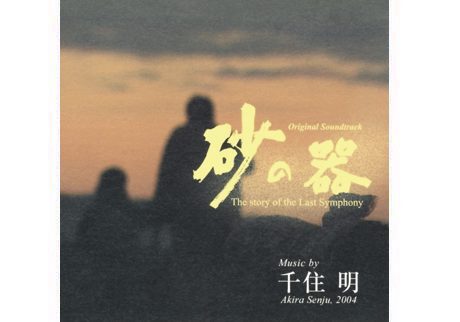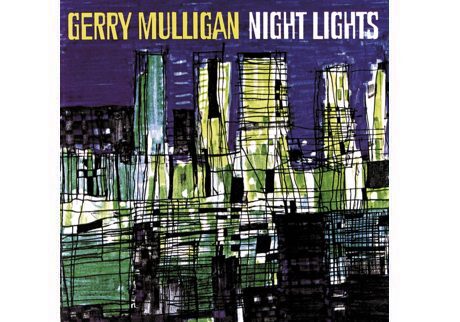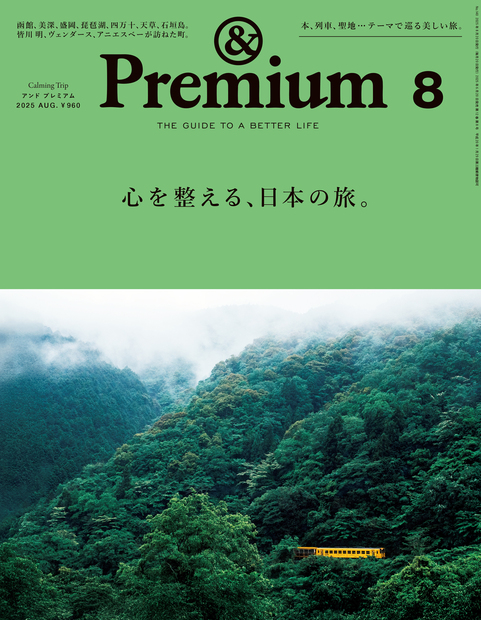江﨑 文武音楽家

1992年、福岡市生まれ。4歳からピアノを、7歳から作曲を学ぶ。東京藝術大学音楽学部卒業。東京大学大学院修士課程修了。WONK, millennium paradeでキーボードを務めるほか、King Gnu, Vaundyなど数多くのアーティスト作品にレコーディング、プロデュースで参加。映画『ホムンクルス』(監督 清水崇、原作 山本英夫)をはじめ劇伴音楽も手掛けるほか、音楽レーベルの主宰、芸術教育への参加など、さまざまな領域を自由に横断しながら活動を続ける。2021年、ソロでの音楽活動をスタート。