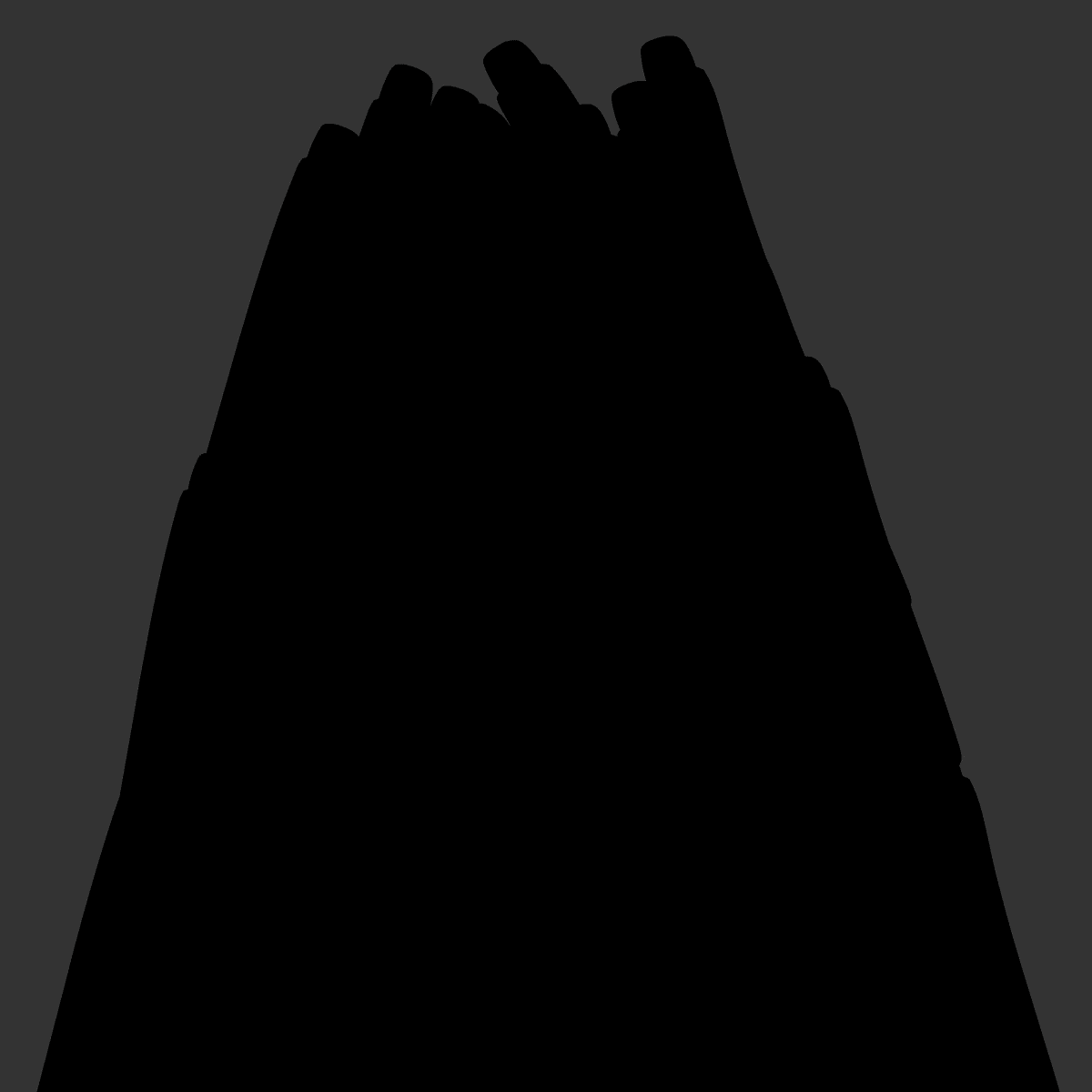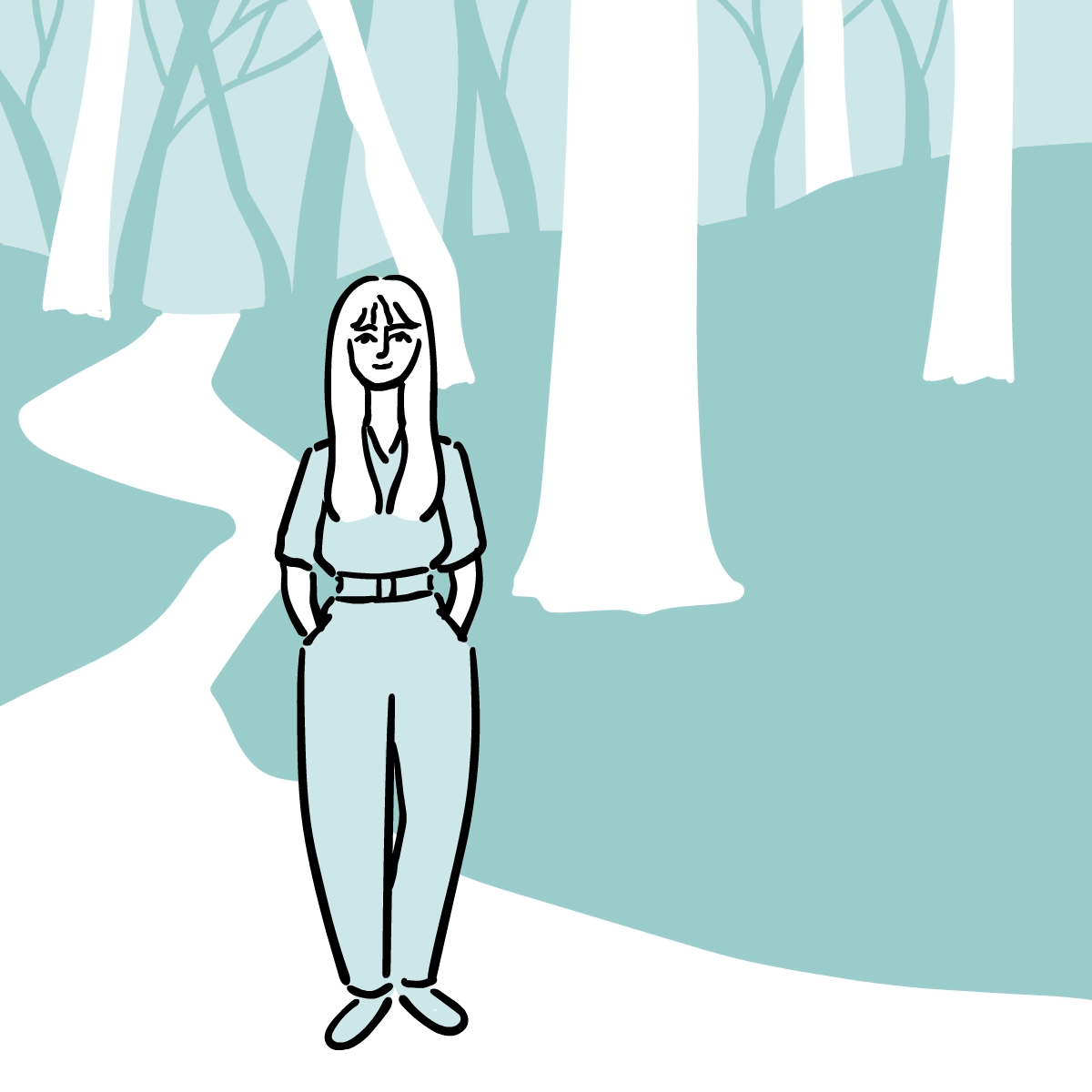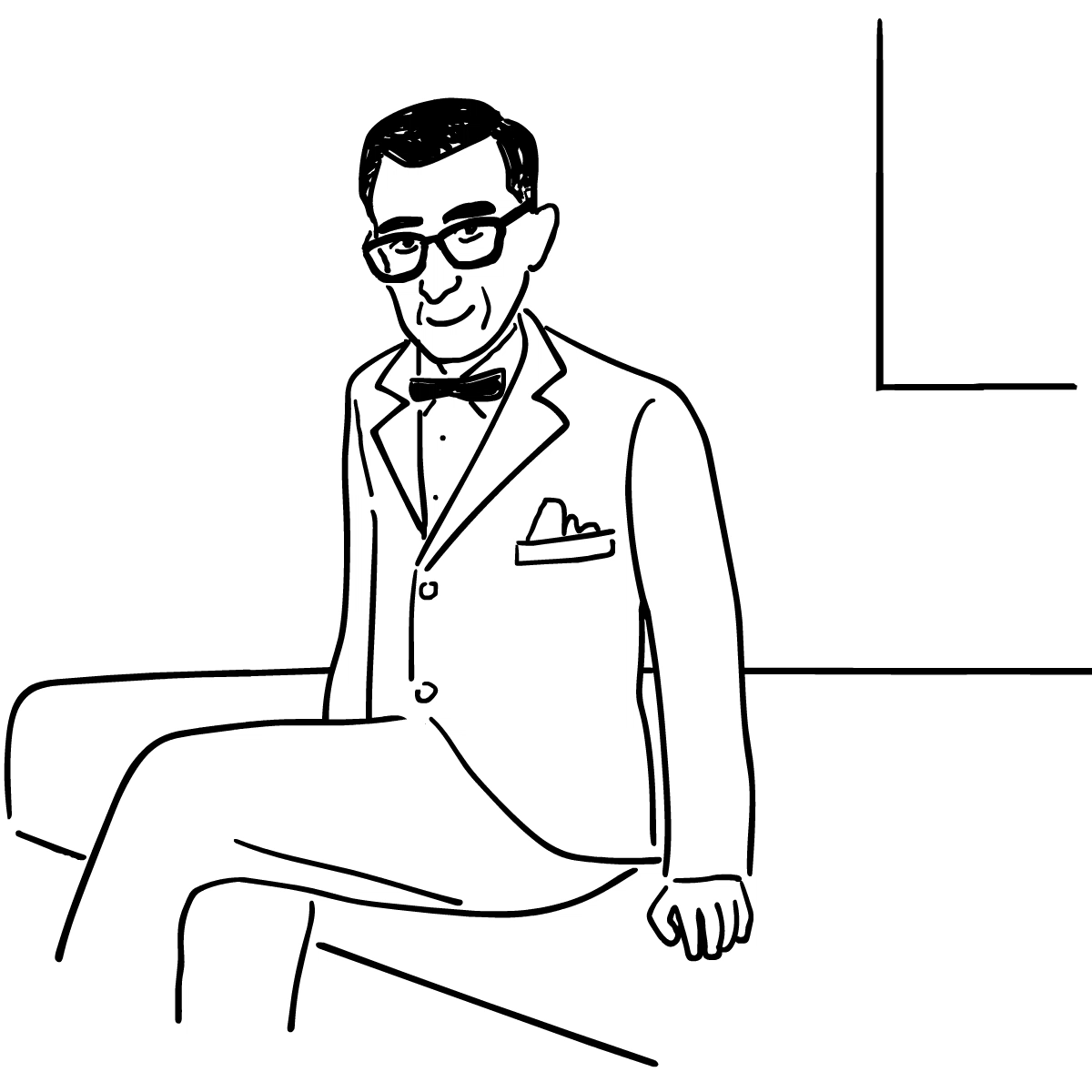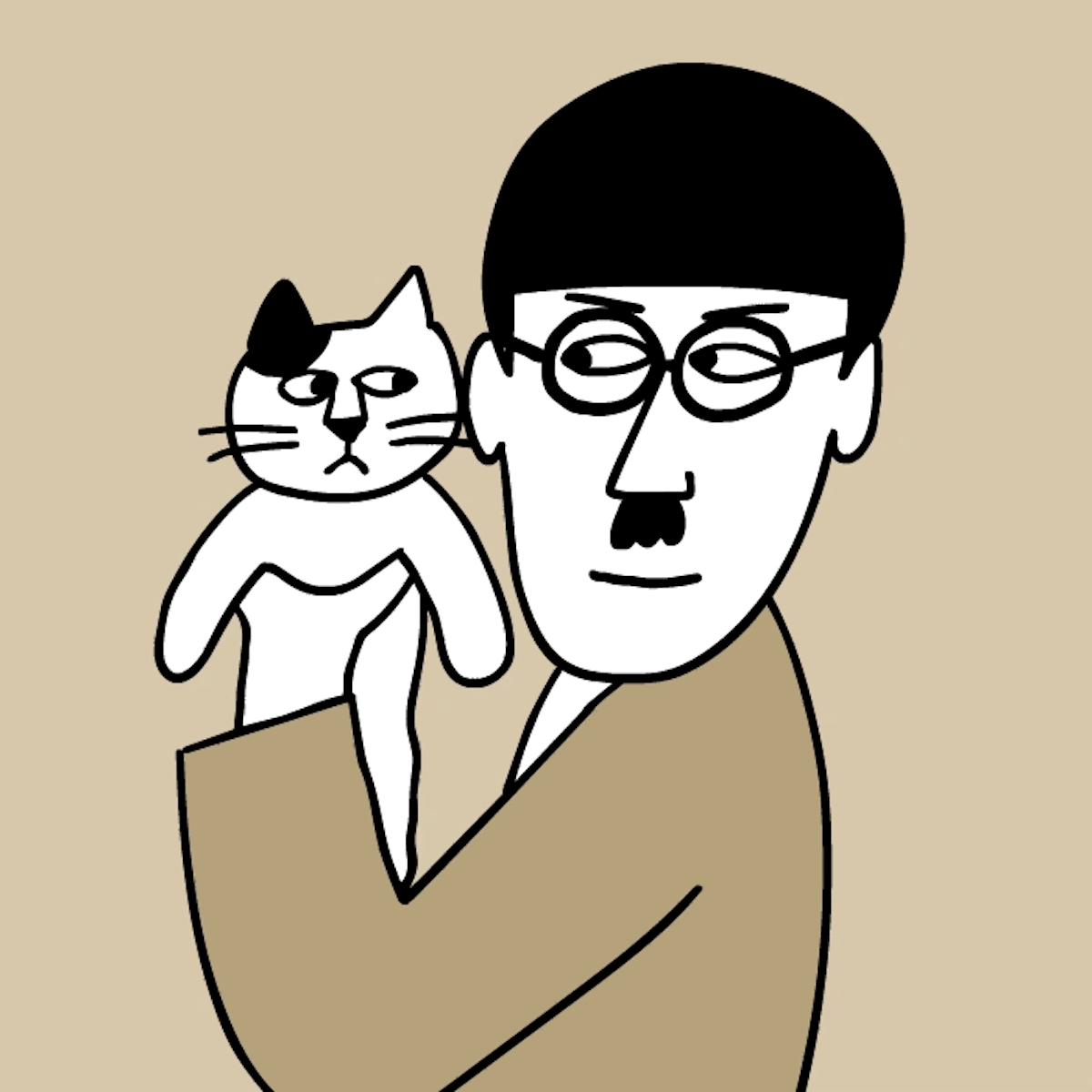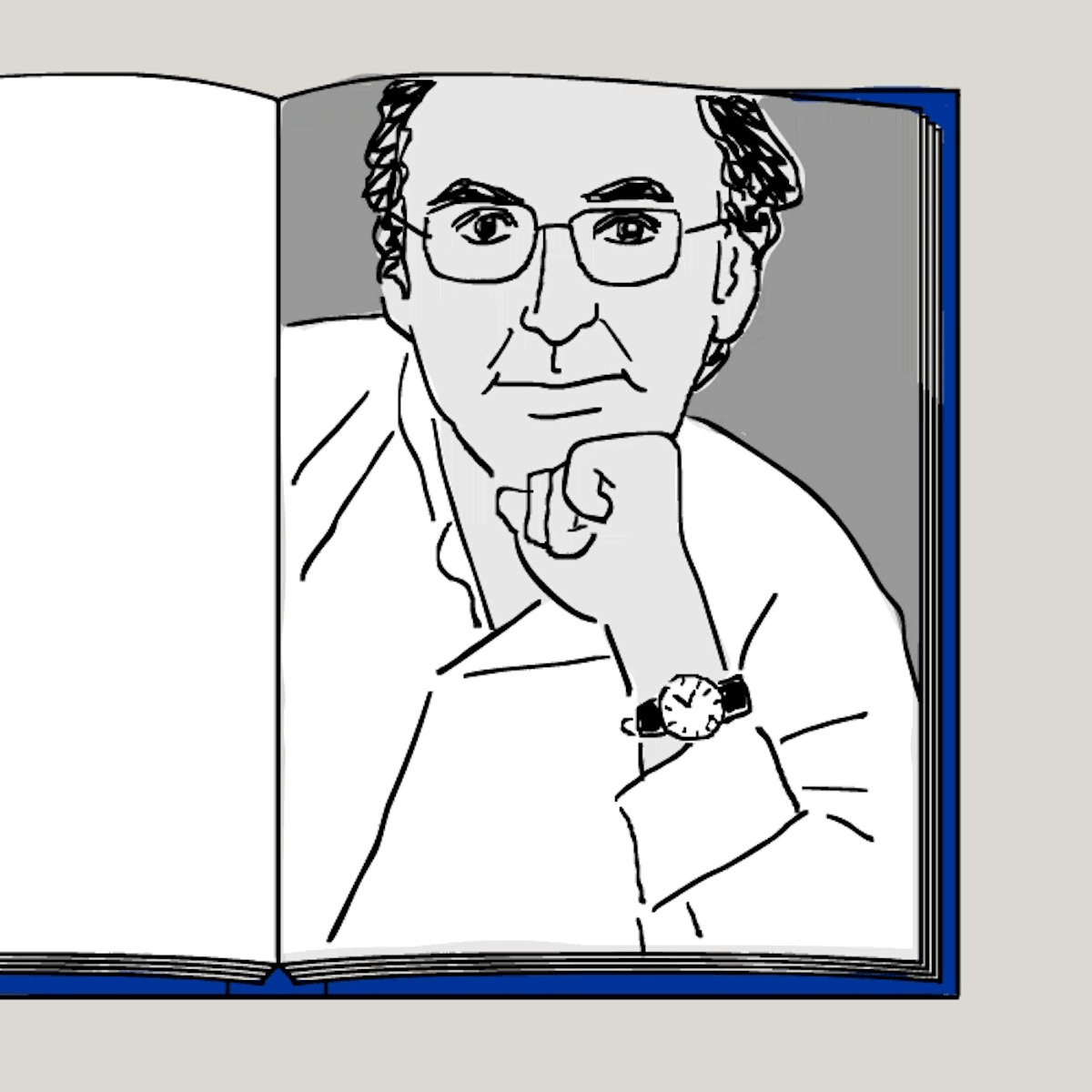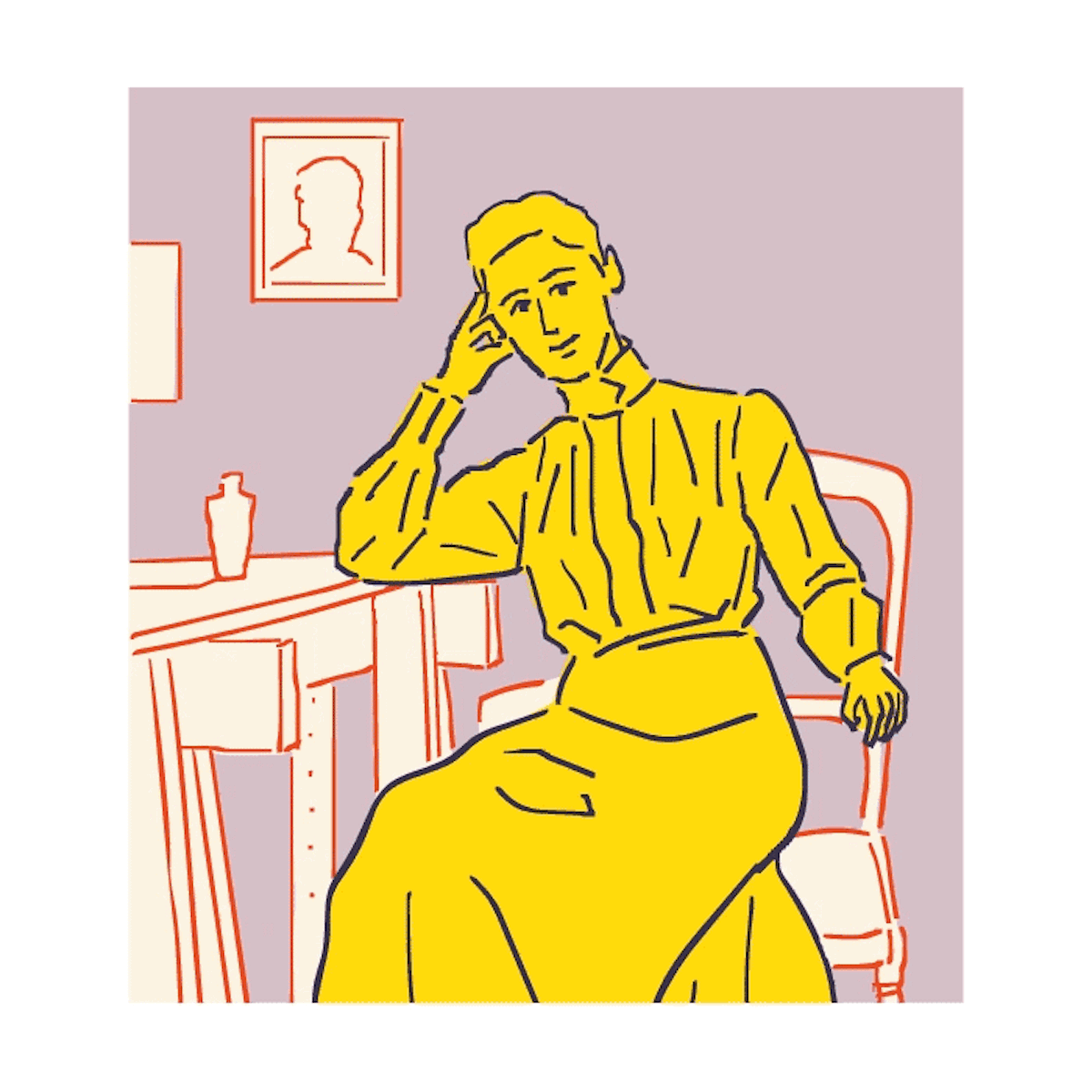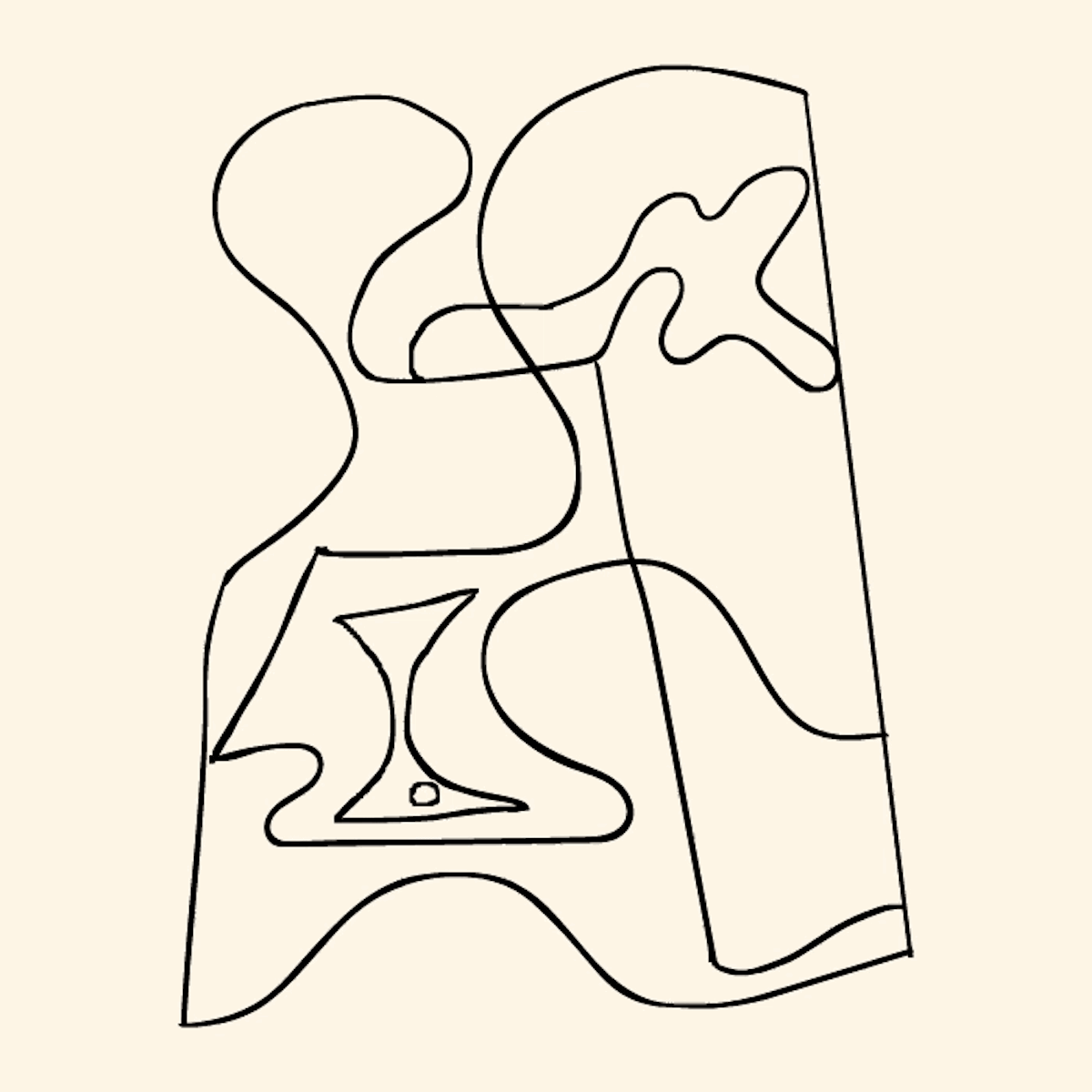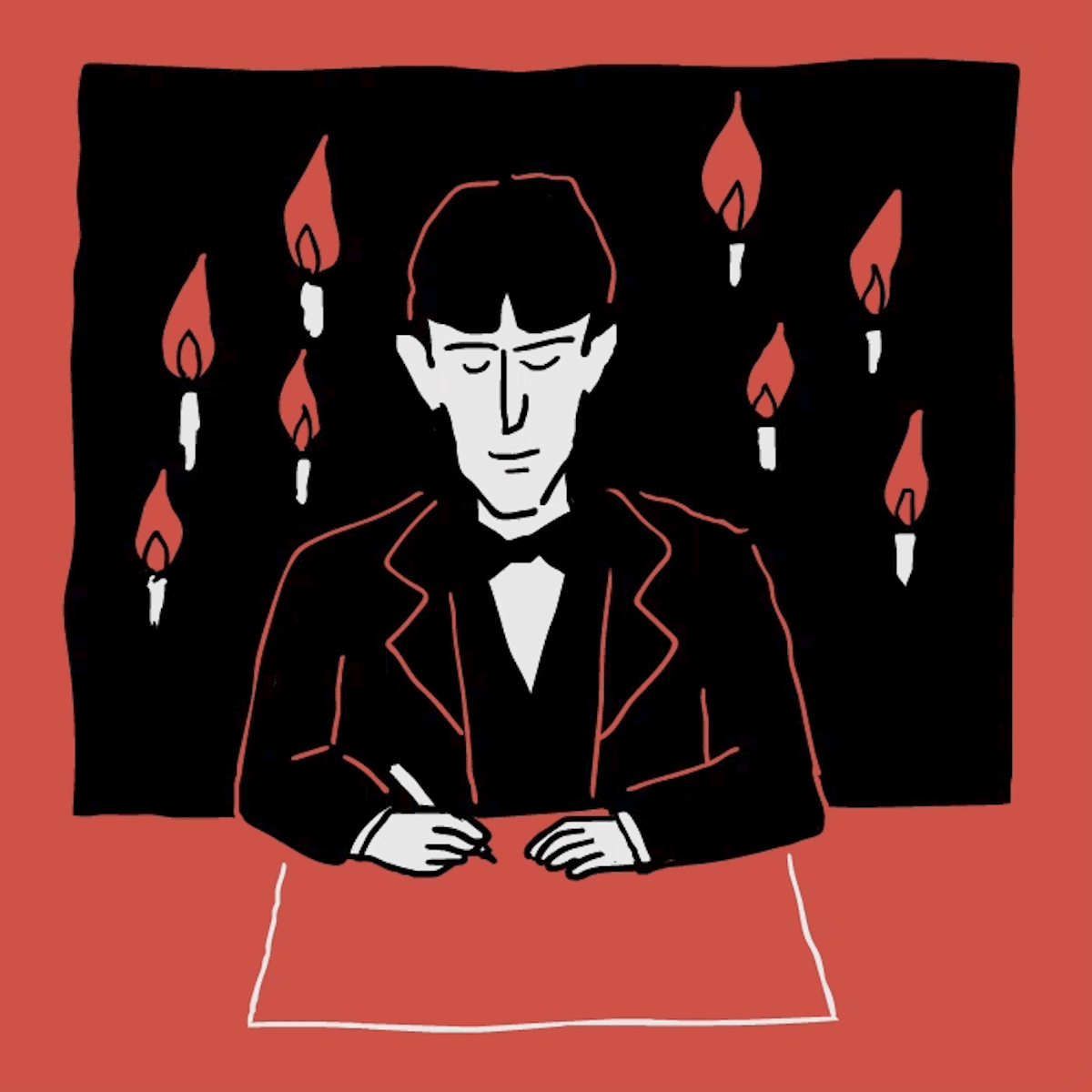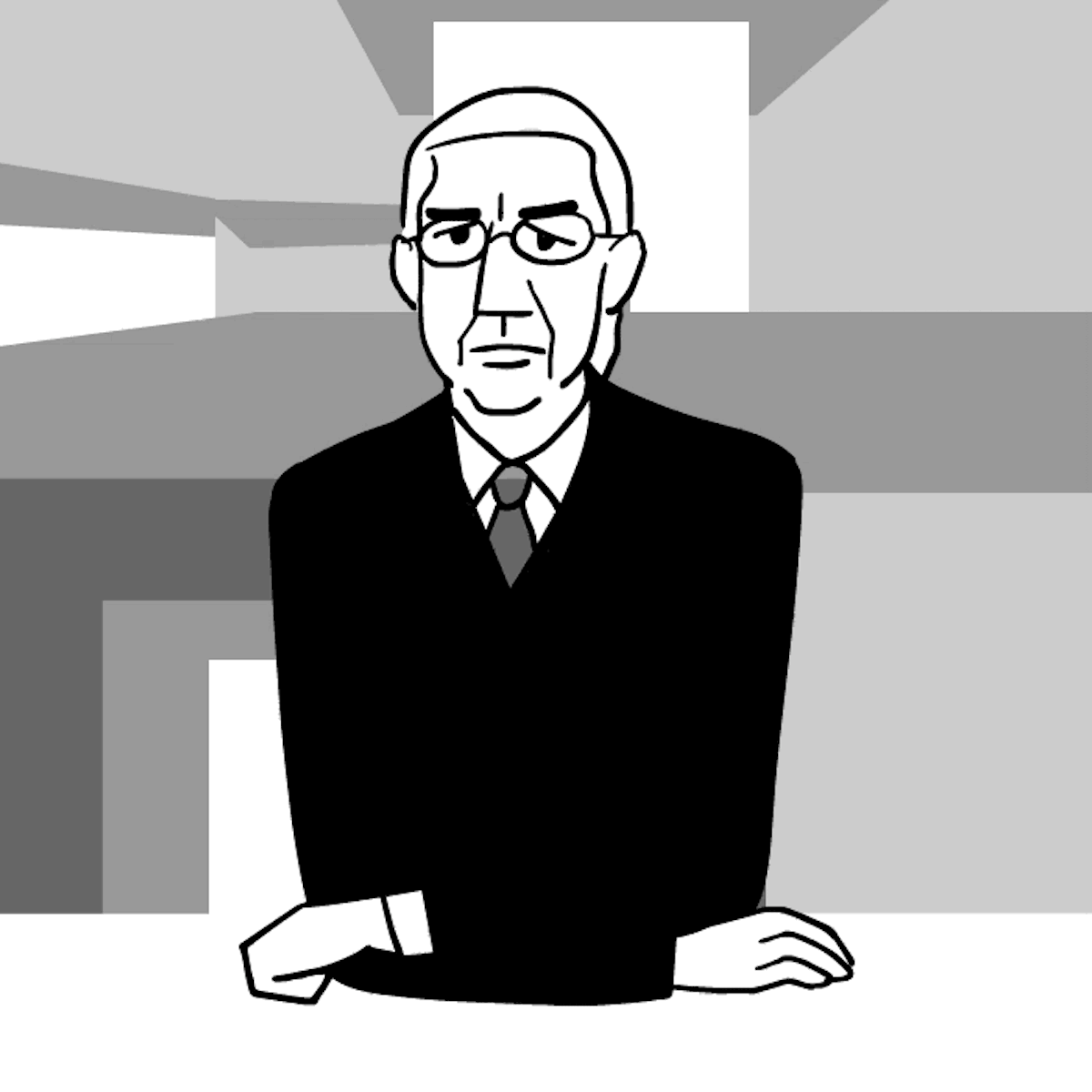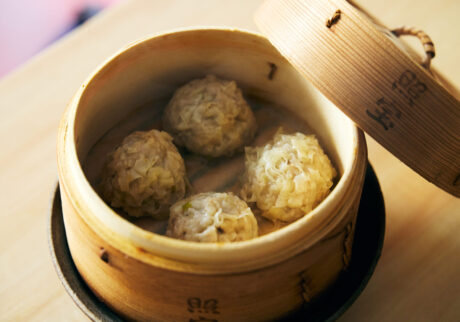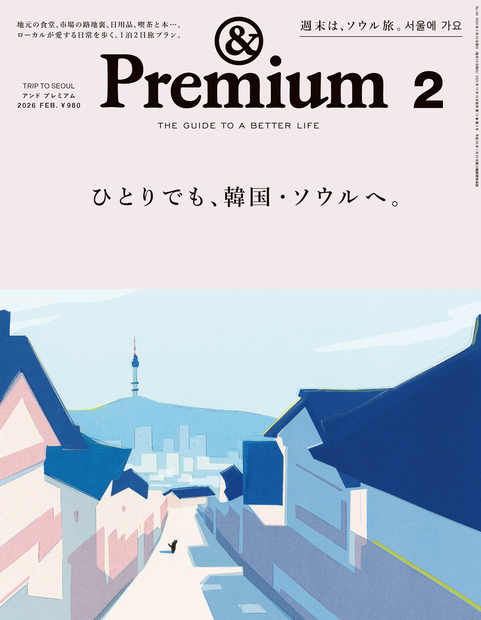河内タカの素顔の芸術家たち。
人の生き方や自然との関係を問い続けた 吉阪隆正【河内タカの素顔の芸術家たち】October 10, 2025
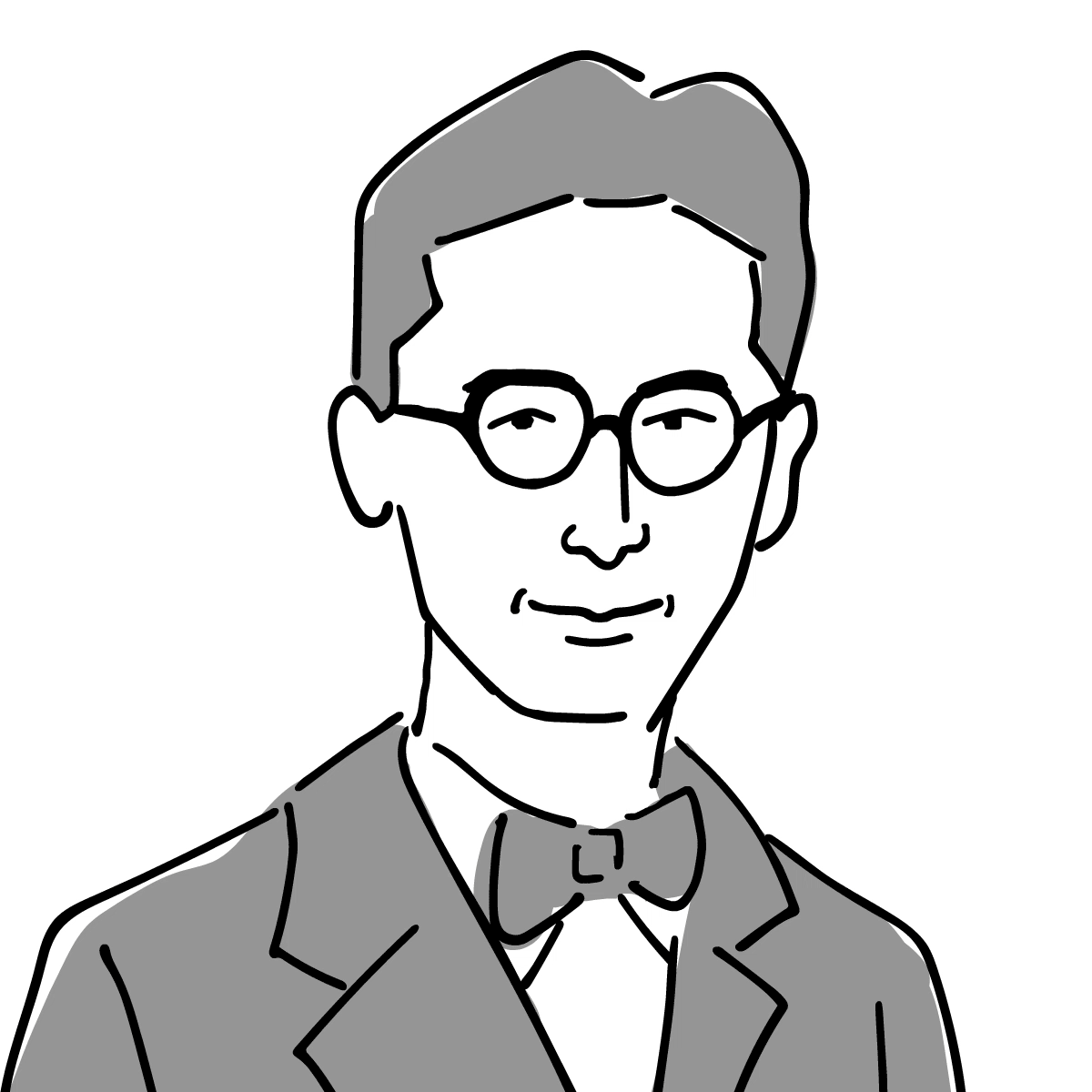
吉阪隆正 Takamasa Yoshizaka
1917-1980 / JPN
#143
東京に生まれ、外交官であった父の仕事の関係で幼少期をスイスのジュネーヴで過ごす。帰国後、早稲田大学理工学部建築学科で学び、生活学の提唱者である今和次郎に師事。1950年に戦後第1回フランス政府給費留学生として渡仏。ル・コルビュジエのアトリエに2年間勤務しチャンディガール計画などに携わる。1954年に自身の設計・研究組織である「U研究室」を設立し、ここから象設計集団など多くの優れた建築家を輩出。独創的な建築作品と思想で戦後日本建築界に大きな影響を与えた。
人の生き方や自然との関係を問い続けた建築家
吉阪隆正
建築家、思想家、そして冒険家であった吉阪隆正は、前川國男、坂倉準三とともにル・コルビュジエの三人の日本人弟子の一人として知られる、戦後の日本を代表する人物です。
1950年、戦後第1回のフランス政府給費留学生としてパリに渡り、ル・コルビュジエのアトリエに入所。1952年まで所員として数々のプロジェクトに携わり、近代建築の神髄を吸収していきました。この時期のル・コルビュジエは、多くの傑作を続々と手がけていた絶頂期で、マルセイユの集合住宅「ユニテ・ダビタシオン」、シェル構造を用いた彫塑的(ちょうそてき)なフォルムの「ロンシャンの礼拝堂」、都市を一から建設するインドの「チャンディガール都市計画」の壮大なプロジェクトなど、新たな鉄筋コンクリートの可能性やモデュロール*1といったノウハウを現場で体得していきました。
ル・コルビュジエの思想や革新的な技術を日本に持ち帰った吉阪は、師の影響を受けながらもそれを単に模倣するのではなく、日本の風土や人の営みに対しての深い洞察に基づいた力強い造形を生み出していきました。例えば、「住宅は住むための機械」と普遍的で合理的な秩序を追求しながら、屋上庭園といった自然を制御し建築と自然を明確に分けたル・コルビュジエに対して、吉阪は人間とそれを取り巻く環境を一体として捉える「有形学」*2を提唱しました。
この有形学が初めて実践された重要な建築が、「ヴェネチア・ビエンナーレ日本館」(1956年)でした。コルビュジエ流にピロティで建物全体を持ち上げることで地面からの解放を目指すのではなく、吉阪のピロティは庭の木々や地面と建築とを緩やかにつなぐ役割が果たしていました。さらに機能的な空間を生み出しながら、内部から庭の緑が効果的に見えるなど、まさに自然と建築が一体となるような設計を行なったのです。
吉阪といえば、「有形学」とともに語られるのが「不連続統一体」*3という独自の思想です。これは建築が周囲の環境から独立して存在するのものではなく、地形や風土と一体化し、自然のサイクルの中に組み込まれるべきだという考え方です。八王子市にある「大学セミナー・ハウス」はこの考えを実践した作品が、大地に楔を打ち込んだような逆ピラミッド型の本館を中心に、自然の地形を巧みに活かした複数の建物が点在するという吉阪の代表作です。
ピンクと紫の壁が目を引く「アテネ・フランセ」は増築が繰り返されたことで、それぞれの増築部分が一体化せず、不連続な形態を保ちながらも全体が構成された建築として知られています。また「住まいは、住み手が完成させる“未完の建築”でよい」とし、住む人が暮らしながら手を加え、変化させていくことで本当の価値を持つという考えが反映されたのが、俳優の鈴木京香さんが購入して話題になった個人邸「ヴィラ・クゥクゥ」です。
聞くところによると、普段の吉阪はニコニコとして優しく、誰にでも敬語を使う温厚さがありながら、いったん設計に向かうと鬼気迫るほどだったそうです。そんな穏やかさと激しさを併せ持っていた思想の根底に「あそび」の精神がありました。何事にも好奇心を持って物事の本質を探求していた吉阪の姿を思い浮かべてしまいますが、そのような熱い探求心は、建築設計だけでなく、キリマンジャロ登頂やマッキンレー登頂の隊長を務めるなど、登山家や冒険家としての活動にも向けられました。世界的に見ても独創的な建築を生み出せたのも、そのような多面的でユニークな人間性があったからかもしれません。
ル・コルビジュエの教えをただ鵜呑みにすることなく、日本の風土や自身の思想と融合させ、新たな建築言語を創造した吉阪の建築は、どこか土着的な力強さを感じさせ、今も色褪せることのない魅力を放っています。それゆえに建築を通して人間の生き方や世界のあり方を問い続けた吉阪の建築や思想が、効率性や均一性が重視されがちな現代社会において、多くの人々を魅了するのかもしれないですね。
1.モデュロール:ル・コルビュジエが人体の寸法と黄金比を組み合わせて考案した建築物の基準寸法を定めるシステム。
2.有形学:機能や見た目の美しさだけではなく、まずそこに住まう人間の「生活」があり、建築はその生活を豊かにするための「かたち」でなければならないという考え方。
3.不連続統一体:一見するとバラバラで矛盾しているような要素が、一つの全体として調和している状態を指す言葉で、多様性を認めながら調和を目指す吉阪の設計思想の核となっていた。

『吉阪隆正|大学セミナーハウス』(建築資料研究社)モダニズム建築の重要作品として知られる「大学セミナーハウス」を通じて、吉阪隆正の活動理論である「不連続統一体」を読み解く一冊。
文/河内 タカ
高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。