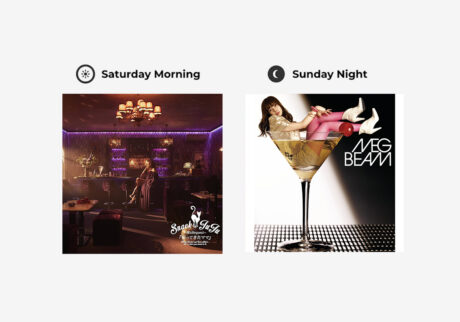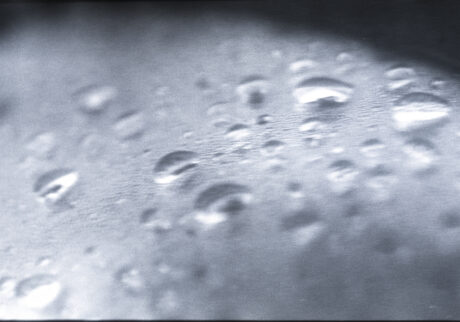LIFESTYLE ベターライフな暮らしのこと。
スタイルのある人たちに会ってきた。モデル・花楓さんの場合。『&Premium』No. 77 2020年5月号より立ち読み / March 19, 2020
2020年3月19日発売の『&Premium』最新号の特集は、「スタイルと生き方」。内面の奥底に生き方のポリシーがある人の、ファッションスタイルやライフスタイルについて掘り下げる1冊です。仕事もプライベートも謳歌するチャーミングな7人の女性たちに会いに行き、力強く人生を切り開いた6人の物語を見つめ、スタイルをつくるベーシックアイテムや、トレンドではなくスタイルをつくる4人の作り手たちの紹介、フランス人のスタイルに対する考え方についても取材しました。ここでは、巻頭の企画「スタイルのある人たちに会ってきた」より、モデルの花楓さんのスタイルを紹介します。
子どもの頃から変わらない、 好きなものに囲まれて。

古いもの、変なもの、自分の中でちゃんと生きるものが好き。
白Tシャツとデニムがいつまでも似合う人がいる。それ自体は聞き飽きたフレーズ、パターン化された女性像かもしれないけれど、それでも、「本当に似合う人」というのは数少なくて、スタイルの奥にある唯一無二の個性に惹かれてやまない。モデルの花楓さんもその一人だ。「可愛いと言われたいと思ったことはなくて、誰かのようになりたいということもない。ただ、かっこよくありたい。息子から『かっこいい』と褒められたら嬉しいですね」と語る。
原点はずっと幼い頃にさかのぼる。「子どもの頃からスカートはほとんどはかず、男の子のような格好ばかりしていました。外国車の輸入販売をしていた父は、アイビーファッションやアメリカンヴィンテージへのこだわりが強い人。私の服は父が選んでいて、その時着せられていたのは、〈コンバース〉のチャックテイラーに〈バーバリー〉のコートなどなど。保育園にレザーパンツをはいていって、先生に怒られたことも覚えています」
好きなものはそれからほぼ変わっていない。たとえば古着。「ヴィンテージのチャックテイラーのくすんだ赤とか、時間を経たデニムの色の具合は、いまからずっと毎日、何年はいたとしても自分では得られない。誰かがはいてくれたからそうなったわけで、ありがたく受け継いで、できるならぼろぼろになるまで長く付き合って、一緒に育っていけたらいいですね」。そこに、心地よいと感じるアイテムを合わせる。革の柔らかさとお菓子のようなカラフルな色合いに惚れ込んで「これさえあれば他にいらないっていうほどきすぎて、いっぱい集めています」という、〈マルティニアーノ〉のフラットシューズ。コットンTシャツは長野・諏訪のセレクトショップで購入。ネックレスは、知り合いのヴィンテージショップのオーナーが身に着けているのを長年〝狙って〞いて、とうとう「散々着けたから売ってあげる」と譲り受けた。それぞれがそれぞれの場所とタイミングで、彼女の元にたどり着くまでのストーリーがある。
着るものだけでなく、身の回りのものを選ぶ目にも、ぶれない軸がある。〈マルニ木工〉のヴィンテージチェアを旅先で発見し、破格の4000円で購入したり、リサイクルショップで掘り出し物を見つけるのも得意で、作家ものの器と古道具とが交じり合って卓を彩る。古い/新しい、高い/安いという基準が取り払われ、愛着のあるものとして等しく居場所を見つけている。
「昔から、なんでそれがいいの? どうしてそれを選ぶの?と人から言われるような〝変なもの〞が目について、気に入ったら客観的な価値を問わず手に入れます。好きかどうかは直感ですが、買うときは、ちゃんと自分の中で生きるものかどうかを考える。ものを駄目にするような買い方はしません。身に着けたり、あるいは思い描いた場所に置くと、ああ、そこに必要だったんだね!と人から納得されることも多いです」
夫と息子の3 人で暮らす自宅のインテリアについては、「99%私の趣味!」と笑う。つい最近、工務店、「オルガンクラフト」とタッグを組んでリビングスペースをリフォームした。テレビと、長年続けているコラージュアートの資料をしまう壁面収納は、塗装や材、照明に至るまで花楓さんが選び抜いた。ピカソの絵を模したタペストリーと中央の写真額(夫であるモデルのShogoさんが選んだ「この家でほとんど唯一の」インテリア)に調和して、帰りたくなる理想の空間になった。「根本にあるのは、身の回りを好きなように飾り、好きなものに囲まれていたい、ということ。見つけて、組み合わせて、自分だけの世界観を表現することをずっと繰り返している気がします」

花楓 モデル
Caede
東京生まれ。モデルとして数々のファッション誌や広告などに出演。現在は、ボランティア活動を通したイベント開催や、デザイナー、コラージュアーティストとしても活躍。2012年に結婚、1 児の母。
photo : Shinnosuke Yoshimori hair & make-up : Megumi Kato text : Azumi Kubota