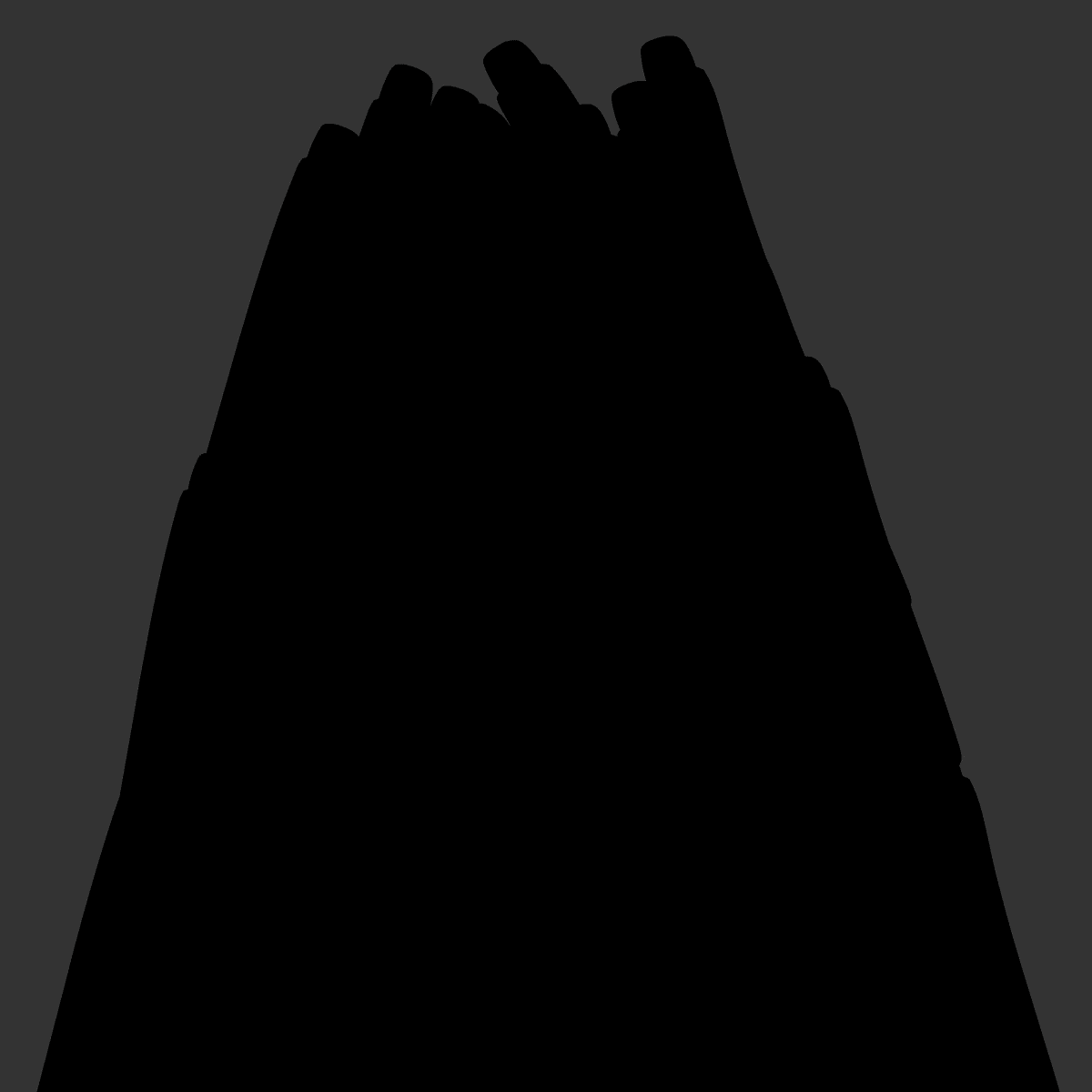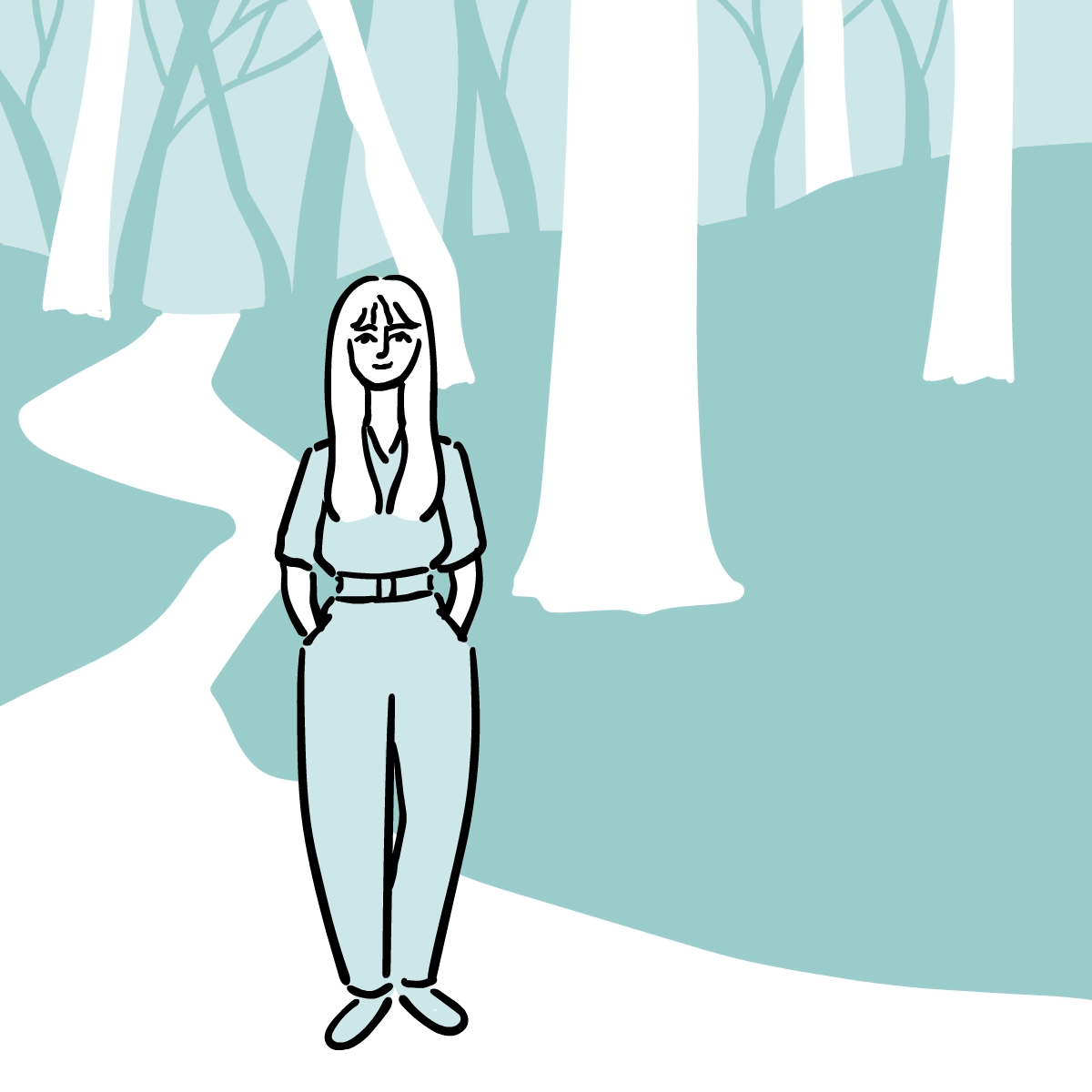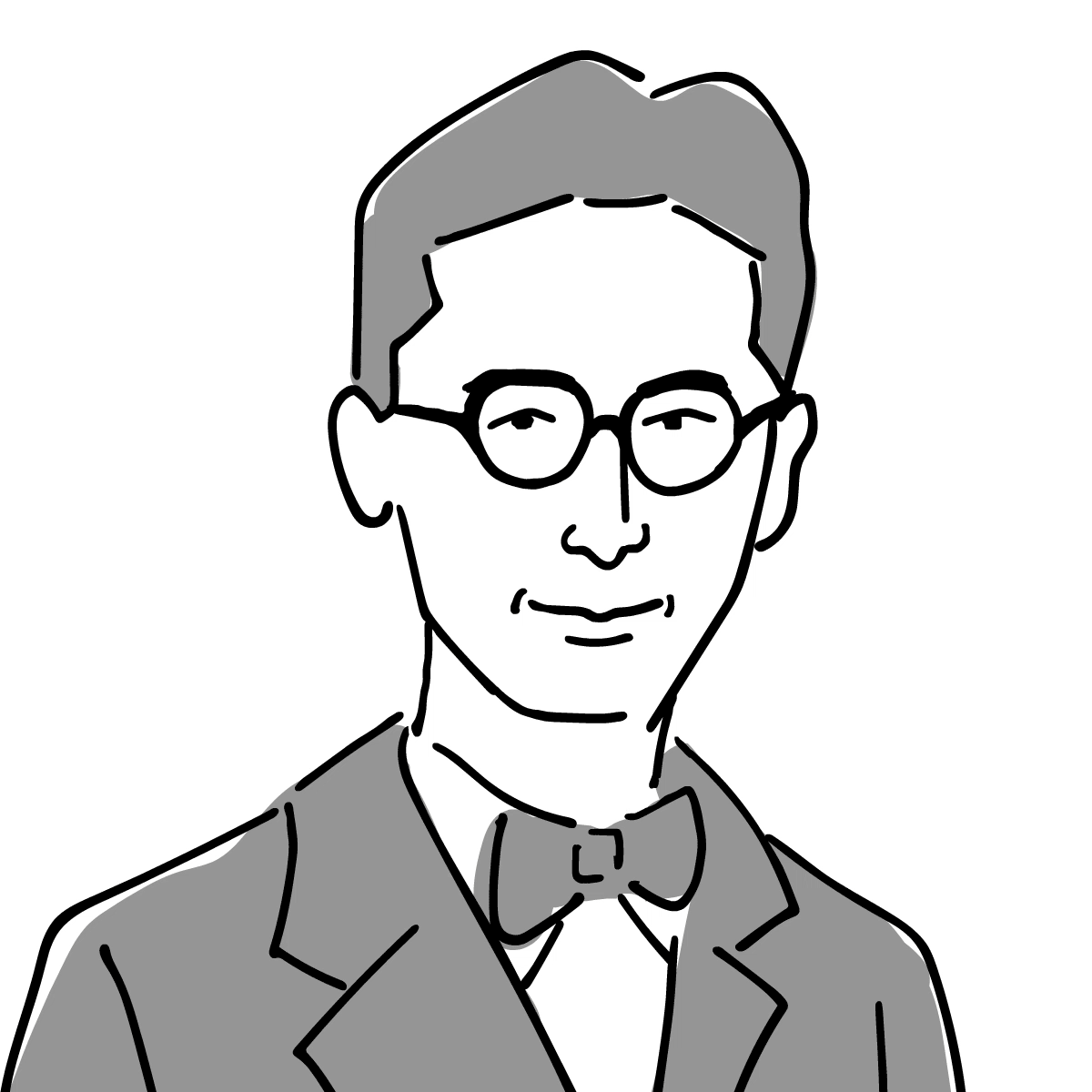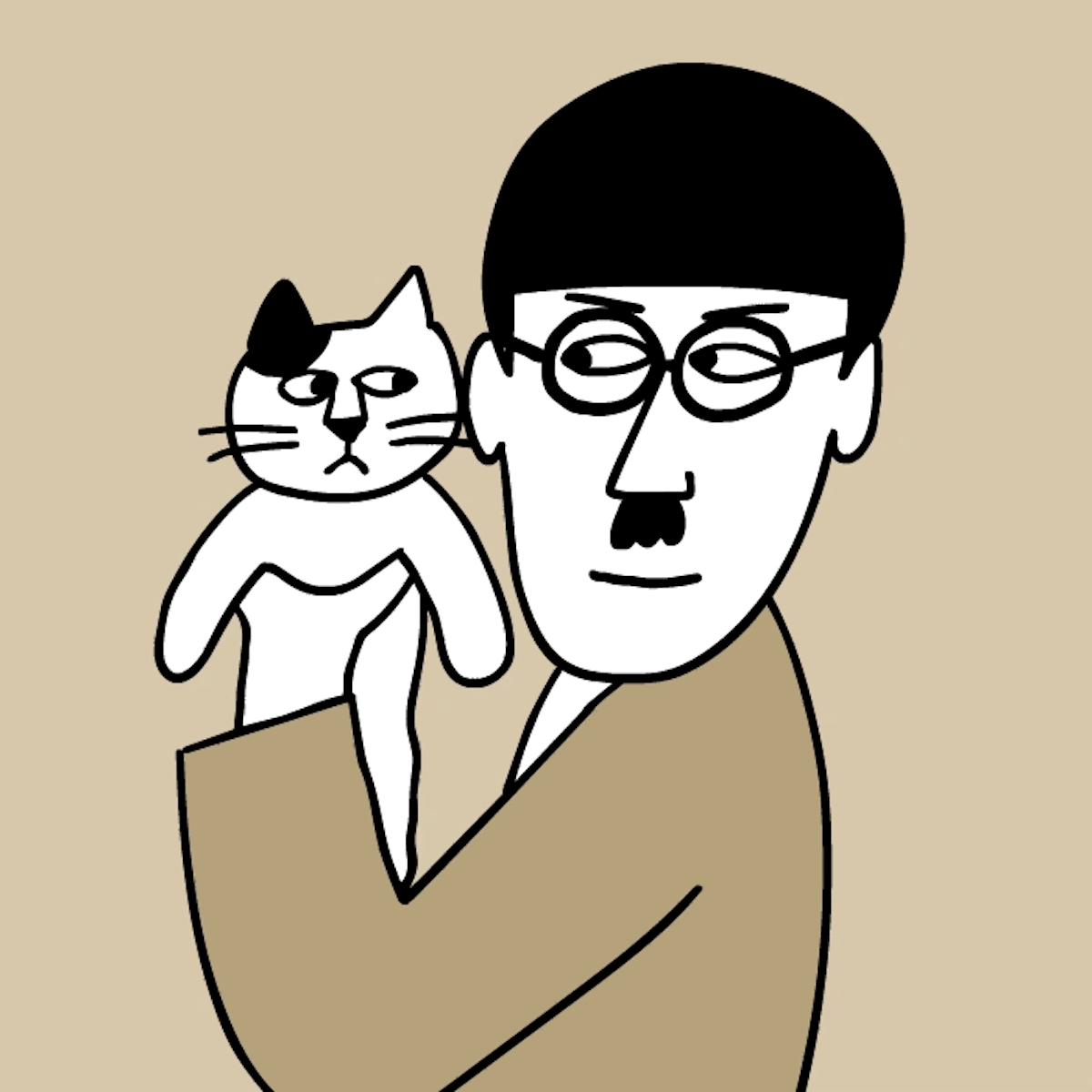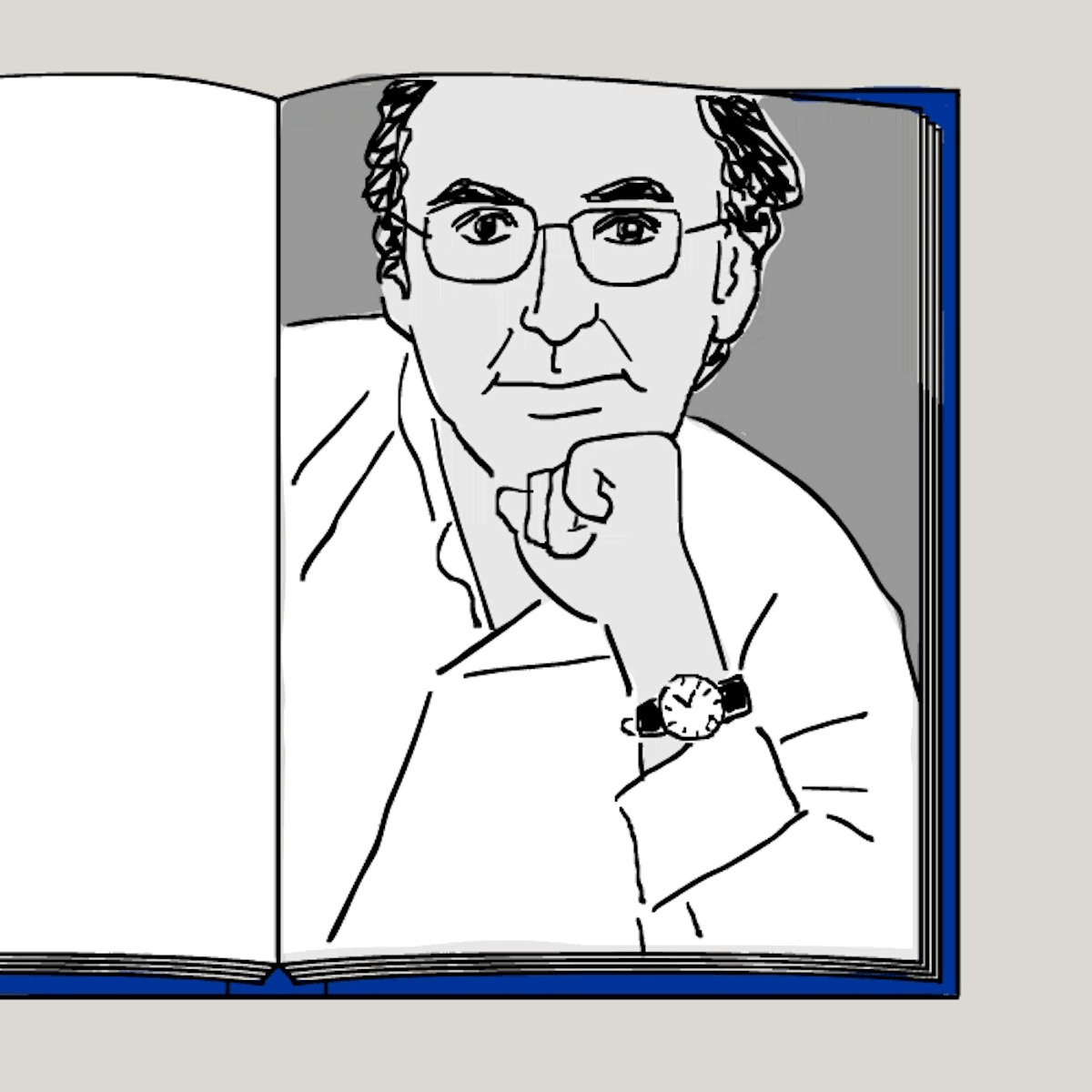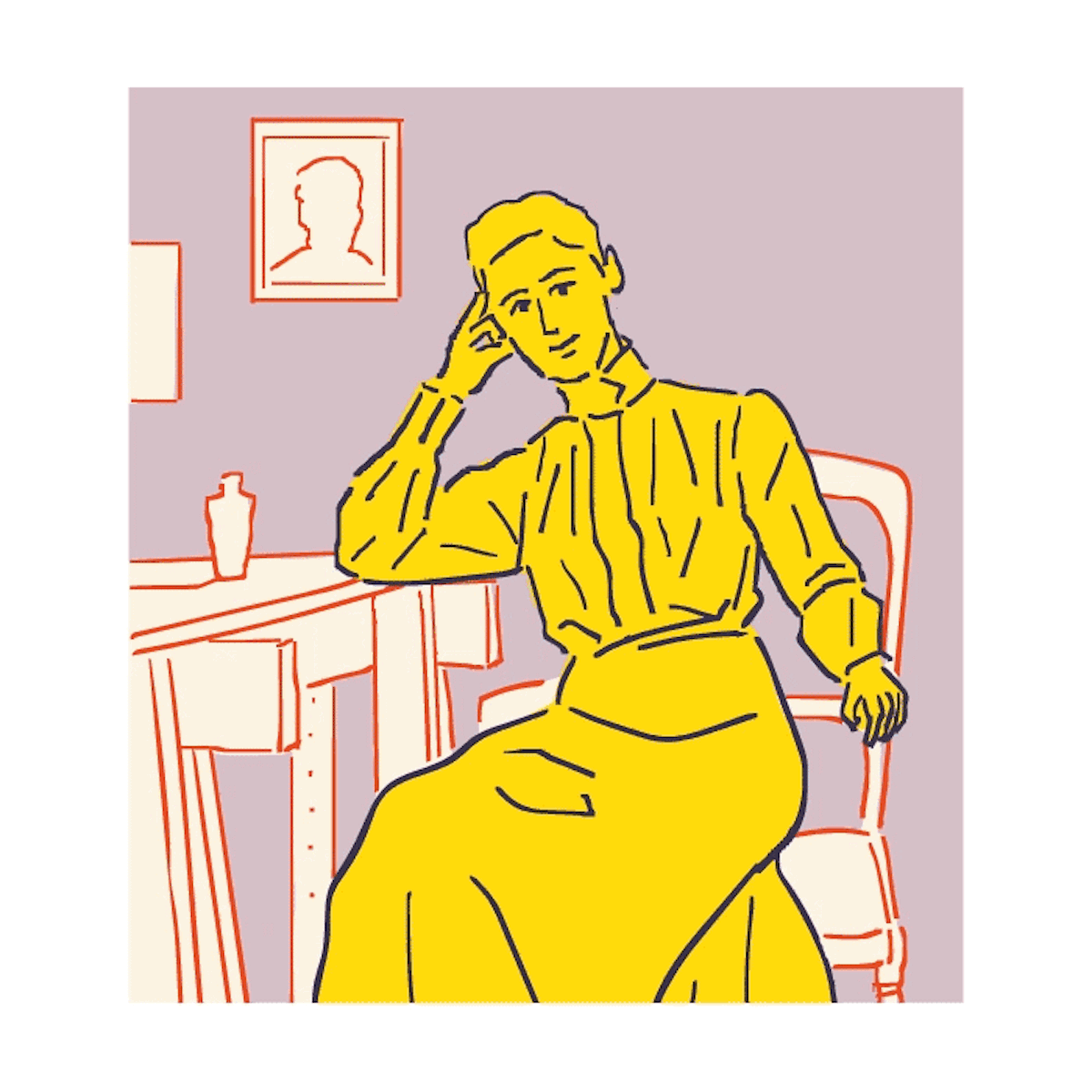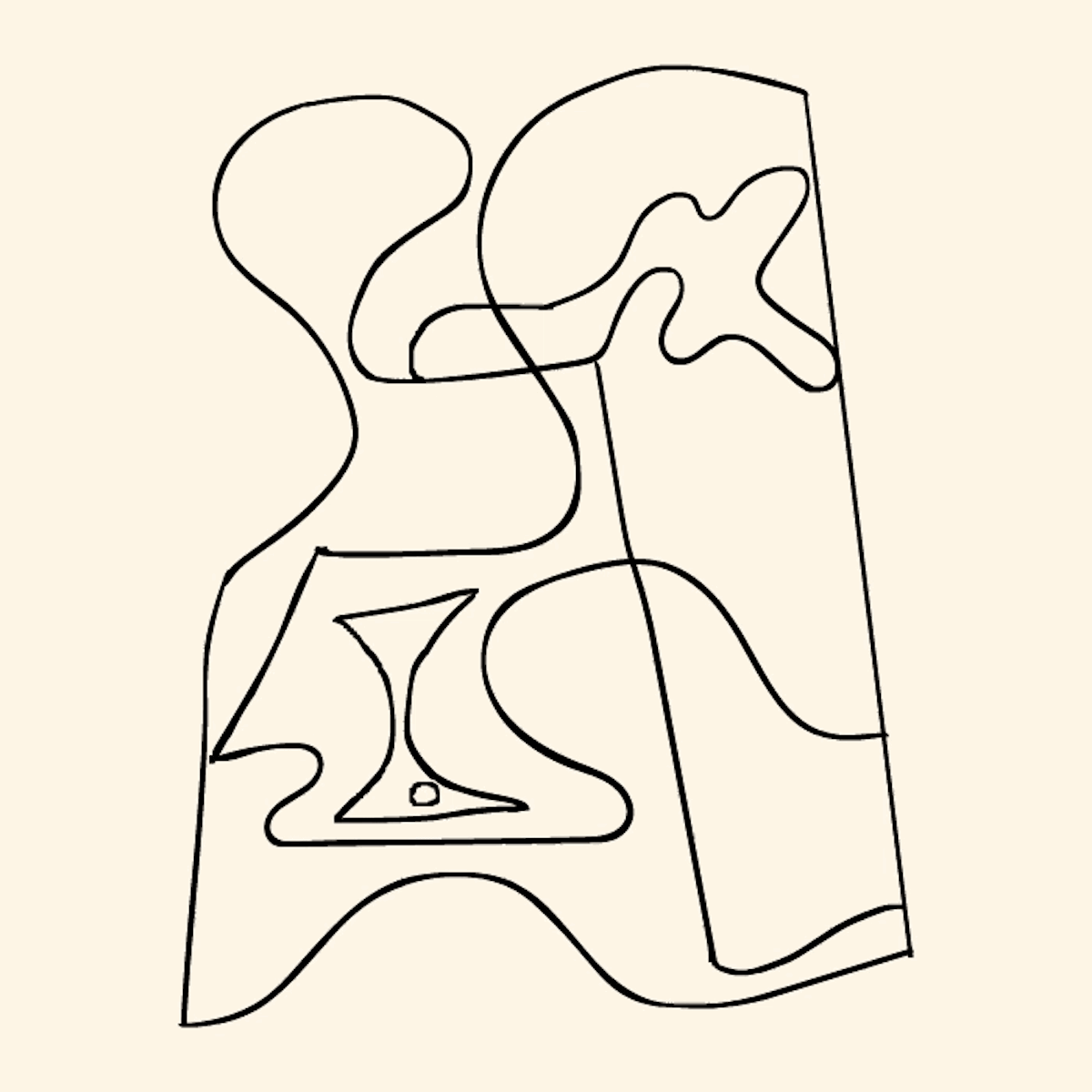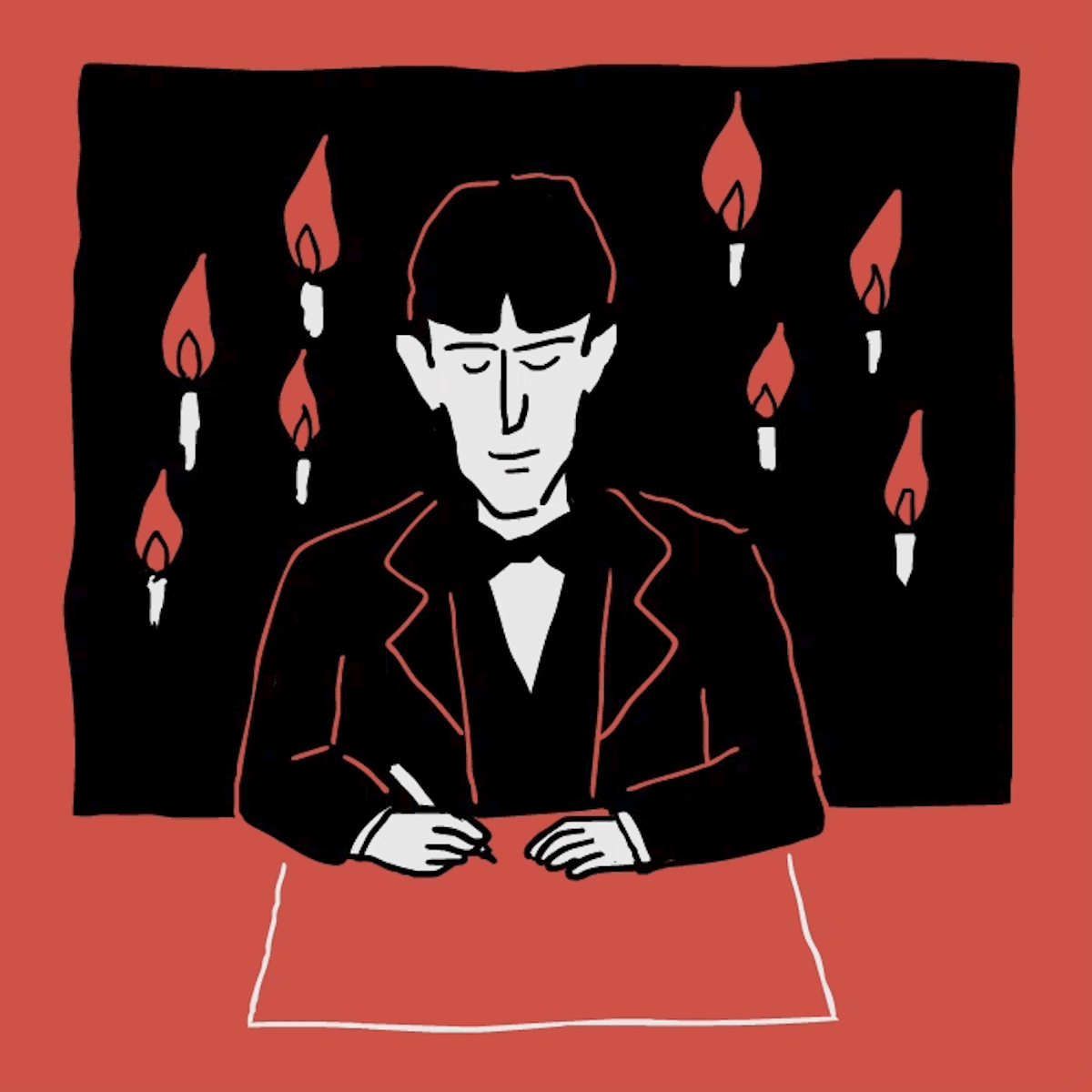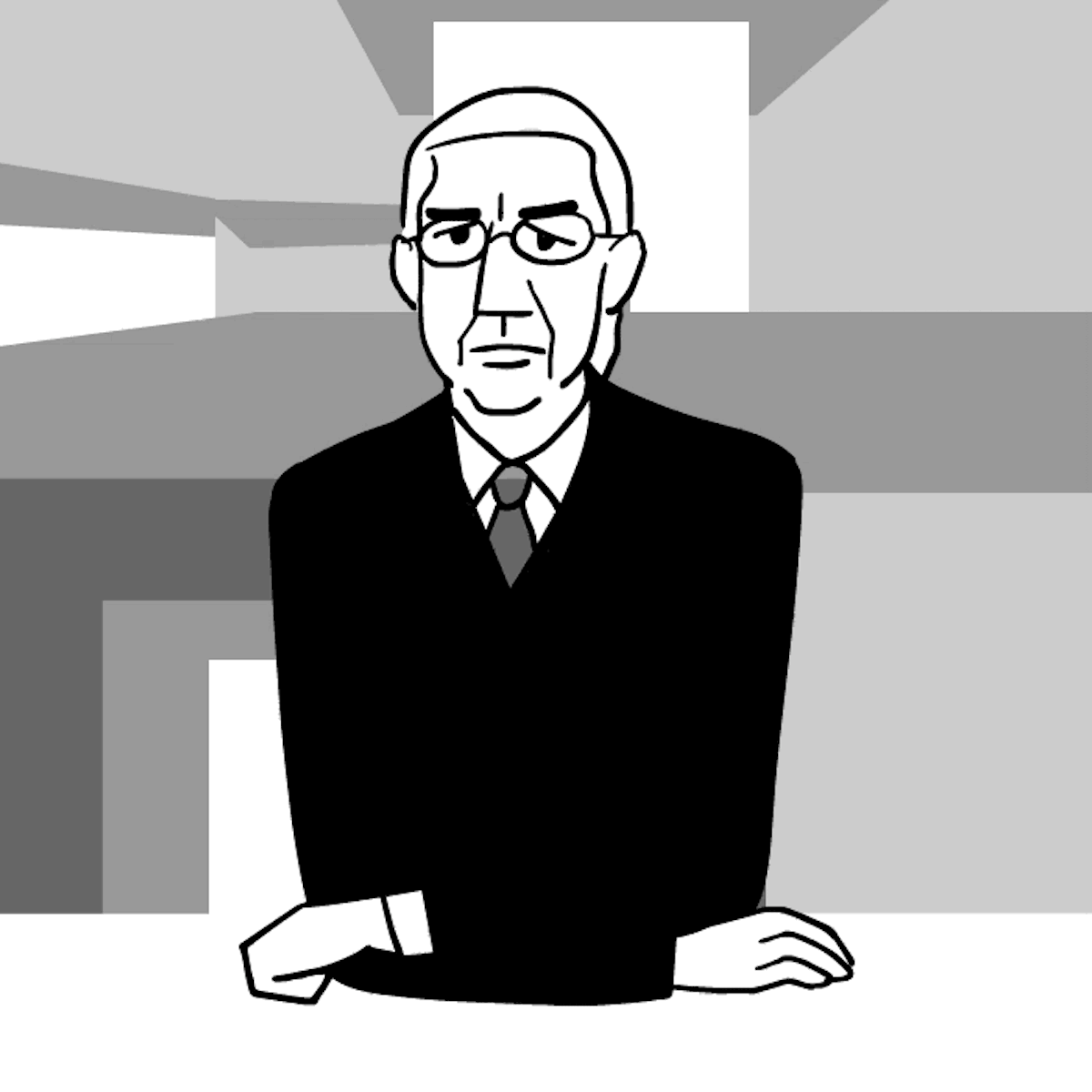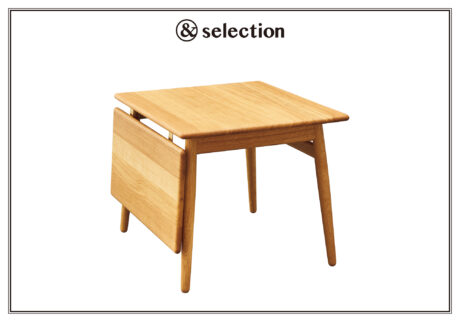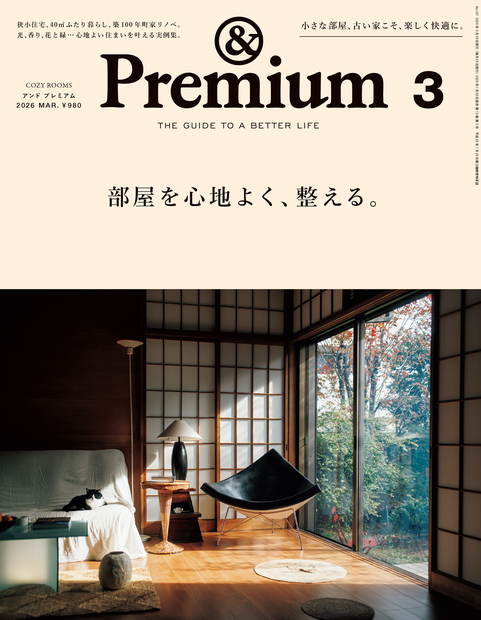河内タカの素顔の芸術家たち。
戦後の日本のモダニズム建築を牽引した坂倉準三【河内タカの素顔の芸術家たち】September 10, 2025
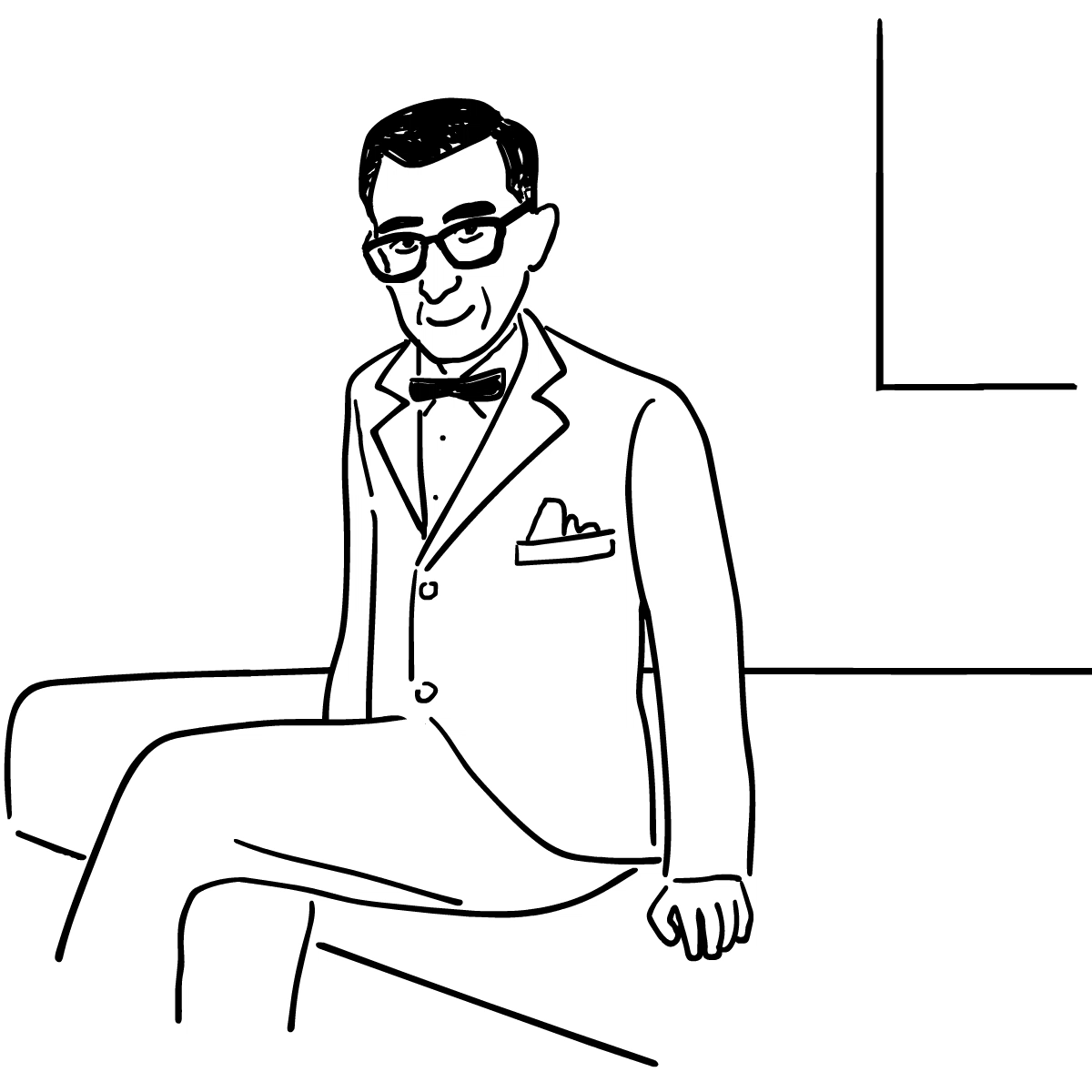
坂倉準三 Junzo Sakakura
1901 - 1969 / JPN
#142
岐阜県羽島郡竹ヶ鼻町(現・羽島市)で酒蔵・千代菊の坂倉又吉の4男として生まれる。東京帝国大学文学部にて美術史を学んだ後、1929年に渡仏し、ル・コルビュジエのアトリエに5年間勤務。一時帰国するもパリ万国博覧会日本館設計のために再びパリへ赴く。1940年に坂倉建築事務所(後に坂倉準三建築研究所へ改称)を設立。常に人間の尺度を基準として考える姿勢を貫きながら、家具から都市計画にいたるまで多様な作品群を生み出した。また、パリ時代に同僚だったシャルロット・ペリアンを日本へ招聘するきっかけを作るなど、⽇本とフランスの架け橋的な存在だった。
戦後の日本のモダニズム建築を牽引した
坂倉準三
「新宿駅西口広場」、「小田急百貨店新宿店本館」、「SHINAGAWA GOOS(旧ホテルパシフィック東京)」、岐阜県の「羽島市庁舎」など、近年、坂倉準三が設計した建築物が解体されるというニュースを目にするたびに寂しい思いをしています。しかしその一方で、「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム(旧神奈川県立近代美術館 鎌倉館本館)」や「アンスティチュ・フランセ東京(旧東京日仏学院)」は共に改修工事が行われて再生され、最近では三重県伊賀市にある旧上野市庁舎が新たにスモールブティックホテル「泊船」*1 として開業しました。用途がなくなった近代建物は容赦なくスクラップ・アンド・ビルドとなる日本の風潮の中、このような再生の事例が増えてくれることを願うばかりです。
坂倉準三といえば、近代建築の巨匠であるル・コルビュジエに師事したことで広く知られていて、コルビジュエの思想を国内で実践するとともに、日本の伝統美との融合を図り、戦後の近代建築の発展に大きく貢献しました。先に弟子入りした前川國男よりも、コルビジュエが提唱した「近代建築の5原則」(ピロティ、自由な平面、自由な立面、水平連続窓、屋上庭園)を実際に体得したのが坂倉で、それに加えて「建築的プロムナード」と呼ばれる人が室内や空間を移動することで風景が変化することを体験させるという設計手法も体得していたのです。
パリのル・コルビジュエのアトリエを退所して帰国したばかりの1936年、坂倉に大きな仕事が舞い込んできました。それはその翌年に開催されることになっていたパリ万博の日本館設計の依頼で、伝統的な建築要素を思わせる独自のデザインが評価され、初めての作品でありながら建築部門のグランプリを受賞するという快挙を達成します。この受賞によって坂倉が単なるル・コルビジュエの模倣者ではなく、日本の文脈で師の思想を独自に展開できることを知らしめ、日本人建築家として国際的な名声を得ることになるのです。
そんな坂倉の建築の特徴として挙げられるのが、周囲の環境と建築の調和です。その最たる例が前述した「神奈川県立近代美術館 鎌倉館」で、細い鉄骨のピロティで建物を持ち上げることにより地面から建築を切り離し、周囲の景観と一体化させました。池の畔に建てられているため、水面に反射する光や緑豊かな自然を内部空間に引き込む手法も素晴らしく、戦後まもなく物資も少なかった1951年に完成したことを考慮すると、ここが日本のモダニズム建築の本格的な始まりを表明した建築とも言っても過言ではないはずです。
一方、その8年後に完成した「国立西洋美術館」は、坂倉とル・コルビジュエの関係性を象徴する建築と言えるでしょう。基本設計はル・コルビュジエが行い、実施設計と現場での監理をル・コルビジュエの弟子である坂倉、前川、吉阪隆正が共同で担当しました。視察のために1955年に来日はしたものの、建造時には現場に来れなかったコルビジュエの意図を適切に汲み取りつつ、日本の法規や技術に合わせて実現するといった師弟の緊密な連携において重要な役割を果たしたのです。後に世界遺産にも登録されたこの建築によって、西洋の近代建築の思想が実際に日本にもたらされ、戦後の日本建築が世界的なレベルへと飛躍する大きな原動力となっていきました。
坂倉が1951年に設計した、支柱が特徴的な「アンスティチュ・フランセ東京」の塔の中の二重螺旋階段における優美な曲線のディテールも忘れてはなりません。この階段は坂倉の作品の中でも際立っていて、そのフォルムや手すりのデザインに見られる人間的な柔らかさのある曲線は、空間に豊かな表情を与えています。坂倉の建築が今なお色褪せない魅力を放ち続けるのも、彼が欧州のモダニズム建築の本質を深く理解した上で、日本の風土と文化に根ざした独自の建築を創造しようとした探求の軌跡を反映されているからだと思うのです。
1. 1964年に坂倉が設計した旧上野市庁舎を再生したブティックホテル。全19室、レセプションは1階、客室は2階となっていて、1階と地下1階には図書館が入っている。再生設計を手がけたのは、公共施設や文化施設の設計を数多く手がけてきた「MARU。architecture」。今回の改修では庁舎の持つ水平ラインや低層構成、周辺の地形や緑とのつながりといった建築本来の魅力を活かしたまま、新たな用途に応じた機能が加えられている。

『坂倉準三|パリ万国博覧会 日本館』(建築資料研究社)日本の伝統的建築の特徴とモダニズムの理念を統合し高い評価を得た「パリ万国博覧会 日本館」の図面と坂倉自身の当時の言葉を掲載。
文/河内 タカ
高校卒業後、サンフランシスコのアートカレッジに留学。NYに拠点を移し展覧会のキュレーションや写真集を数多く手がけ、2011年長年に及ぶ米国生活を終え帰国。2016年には海外での体験をもとにアートや写真のことを書き綴った著書『アートの入り口(アメリカ編)』と続編となる『ヨーロッパ編』を刊行。現在は創業130年を向かえた京都便利堂にて写真の古典技法であるコロタイプの普及を目指した様々なプロジェクトに携わっている。この連載から派生した『芸術家たち 建築とデザインの巨匠 編』(アカツキプレス)を2019年4月に出版、続編『芸術家たち ミッドセンチュリーの偉人 編』(アカツキプレス)が2020年10月に発売となった。